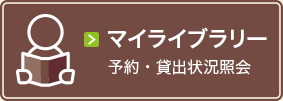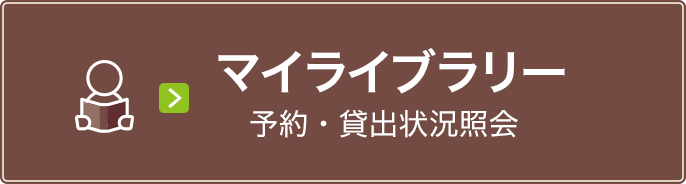令和6年度 岡山県子どもの読書活動推進連絡会 実施報告
テーマ
「中高生の読書支援」
日時
令和7年1月31日(木) 10:30~16:00
会場
岡山県立図書館 2階 多目的ホール
及び Web会議システム「Zoom」を活用したオンライン
参加者
来場
50名〈公共図11名、学校21名(うち小学校6名、中学校9名、高等学校6名)、ボランティア8名、その他教委等5名、取組発表者5名〉
オンライン
46名〈公共図5名、学校38名(うち小学校11名、中学校15名、高等学校12名)、ボランティア2名、その他1名〉
主催
岡山県立図書館
概要
①岡山県における子どもの読書活動推進について
岡山県教育庁生涯学習課
【当日資料はこちら】
県は、岡山県内の小・中学生及び高校生の読書活動の実態を把握し、不読率の低減等に向けた効果的な施策を検討するため、令和6年度「子どもの読書の実態に関する調査」を実施した。調査の結果、小学生の不読率は8.7%、中学生は12.2%、高校生は43.3%と、全校種とも前回調査より改善した。不読の理由としては、小・中学生では「読みたい本が無かったから」、高校生では「本を読む時間が無かったから」の回答割合が高かった。また、本の入手方法としては、校種進行とともに、学校や地域の図書館で借りるケースが減少し、自分で本を購入するケースが増加する傾向にあった。
また、電子書籍のニーズが高校生をはじめ一定数あることから、紙の書籍に加えて電子書籍など多様な読書機会を提供することや、不読者の中にも月1回以上学校図書館を利用している児童・生徒が一定数いることから、学校図書館を通じて読書支援を行うことも効果的であることが示唆された。
今後の方針として、県では引き続き子どもの読書活動の実態把握・分析を継続していくとともに、地域や家庭、学校等と連携しながら、子どもの読書活動推進に取り組んでいきたい。
②取組発表
津山市立成名小学校
【当日資料はこちら】
本校では、令和3年度から子どもたちの読む力・豊かな心の育成を目指し、様々な読書活動に取り組んでいる。そのうち3つを紹介する。まず、読みごたえのある長い物語本に挑戦する「読書力チャレンジ」について、図書室内にある本から吟味して選書し、現在300冊を揃えている。チャレンジ中の児童には声掛けしたり、物語や登場人物の整理など支援を行ったりしているが、無理強いはせず、いつでも別の本に挑戦できるようにしている。読後は認定テストを行い、読書力認定証が授与される。学年全員が認定されればスーパー学年賞の表彰を受けたり、通算100枚目などの認定者にはぴったり賞としてお祝いしたりし、児童の読書意欲を高める工夫をしている。認定者数は取組開始以降、右肩上がりに増加している。読書力チャレンジを通じた成功体験が自己肯定感や読書意欲、認め合いの心などの向上につながっている。自発的な読書へ繋ぐために個別の読書支援も行っている。
次に「読書記録カード」について、年2回長期休暇中に読んだ本の感想を絵を添えて記録するもの。全てのカードを校内に掲示することで本や友達への関心が増え、カードを見て図書室に来る児童が増えるなど読書の輪が広がっている。
最後に図書委員会の活動について、毎年実施する図書室マスコットキャラクター募集やおはなし会、福袋など主体的かつ意欲的に企画・運営しており、どの学年も図書室は楽しい場所というイメージができている。今後も工夫を重ねて多角的に取り組んでいきたい。
美咲町立加美小学校
【当日資料はこちら】
本校の図書館教育の基本理念として、読書活動を通して、読書の喜びや楽しさを体験し、学びへの興味・関心を高めること。また、情報活用能力や問題解決能力を育成することとしている。これを教職員で共通理解し、本校のスローガン「幸せを創り出す力を子どもたちに」のもと、定期的にまたはイベントとして取り組んでいる主な3つを本日紹介する。まず、5年前から取り組んできたブックトークについて、週末の課題を読書のみとし、読んだ本を紹介する資料作りを行い、次週の月曜日の国語の時間に紹介する一連の活動を年6回実施している。また、2年前には系統的に目指す姿を示し、意欲を喚起するため、指標としてルーブリックを作成した。ブックトークの活動については、保護者への理解を促す文書を毎年通知している。どの子も積極的に取り組んでおり、読書への興味に繋がっている。
次に、BT1グランプリについて、年1回ブックトークの集大成として2月に各学年の代表者が出場するブックトークグランプリを昨年度から実施している。図書委員会の主催で行うもので、よいロールモデルになっている。
最後に、委員会活動について、ブックトークを継続する中で、年を追うごとに主体性が生まれてきている。今年はハロウィンやクリスマスなど自主的な活動も多く行われている。
こうした実践の成果としては、「月末はブックトーク」が学校文化になり、本の楽しさを紹介し共有し、新たな本との出会いから楽しさを見つけるという好循環が生まれ、読書による幸せづくりが実現している。
和気町立和気中学校
【当日資料はこちら】
本校は、平成29(2017)年度からの地域学校協働本部事業の開始を見据えた平成28(2016)年度に中学生への読み聞かせと中学生による幼保一体型施設での訪問読み聞かせを始めた。中学生への読み聞かせは、読書の楽しさを実感する機会とすること、生徒の聴く力・創造する力の育成を図ること、地域社会との繋がりを感じる機会とすることを目的としている。年間行事として各クラス年3〜4回、10分間の朝読書の時間に実施している。ボランティアは当初、中学生が絵本をどう感じるかや絵本選びに不安もあったが、今では「中学生に読みたい本がある」と意欲的に活動している。また、当初は戸惑いを見せていた生徒も、絵本の魅力を理解し、楽しんで参加している様子である。ボランティアの方々の優しい語り掛けと温かい眼差しが生徒の成長の糧となり、豊かな時間となっている。
続いて、中学生による訪問読み聞かせは、地域への貢献、ボランティアによる奉仕の精神を養うことを目的として同年に開始した。年1回文化委員会の活動として行い、令和6年度は有志生徒を加えた8名が参加した。活動開始以降、延べ83名の生徒が携わった。生徒たちは園児と読書の楽しさを分かち合い、喜んでもらえたという経験から自信となっている。
また、訪問読み聞かせを行うにあたり、平成30(2018)年度からは、事前研修として町立図書館が中学生のための絵本講座を実施している。読み聞かせボランティアが講師を務め、将来、教員や保育士を目指す生徒たちも参加可能としている。
今後の課題は、生徒の減少や教員の働き方改革など、学校生活や生徒を取り巻く環境変化への対応であるが、状況に柔軟に対応しながら活動を続けていきたい。
岡山県立倉敷古城池高等学校
【当日資料はこちら】
定期的な取り組みとして、美術や古典の授業で制作した成果物の展示や入試対策、勉強になる漫画コーナーの設置など、生徒も教員も立ち寄りやすい図書館づくりをしている。図書館の広報にはLibFinderを使用し、Google Classroomでの図書館だよりの配信など、ICTを積極的に活用している。平成28年度からは各学期に1回、クラスごとに昼休みに本を借りる日を設定した「昼読」を実施。定期的な実施により生徒が図書館に足を運ぶ意識付けになっている。
図書委員が主体の取り組みでは、平成25年度から文化祭のオープニングイベントとして「藤花祭クイズ大会」を毎年実施。コロナ禍を経て現在はGoogle Meetでのオンライン開催をしている。平成28年度から開催している「図書館大賞」は、読んだ本について30字以内のキャッチコピーを考える部門と手書きPOP部門の2部門があり、クイズ大会の得点にも加算される。近くの公共図書館で展示した年もあり、生徒の読書へのモチベーションに繋がっている。また、読書LHRで実施している推し本バトルでは、各自が推しの一冊を2分で紹介し、最後にクラスのチャンプ本を決める。読書LHRをきっかけにして多くの生徒が図書館で本を借りている。
試行錯誤を繰り返しながら続けてきた取り組みが、生徒たちの学校生活の中に定着していることを感じている。学校生活に欠かせない図書館としてこれからも生徒・教職員で力を合わせて活動していきたい。
灘崎文庫くるりんぱ
【当日資料はこちら】
灘崎町に図書館がなかった昭和56(1981)年当時、有志で灘崎町西紅陽台子ども文庫を立ち上げた。7年後の昭和63(1988)年には蔵書2,400冊、利用登録者数約200名となった。その頃から生涯学習の機運が高まり、町では新たに建設される町民会館内に図書館ができる計画があり、そこで活躍するボランティア養成のための講座を平成4(1992)年に受講した。同年12月には子どもまつりを開催し、子ども文庫メンバー3人を含む9人のメンバーで「灘崎文庫くるりんぱ」が始まった。2ヶ月ごとに、読み聞かせやストーリーテリング、パネルシアター等で「おはなしひろば」を開くとともに、児童館や保育園への定期的な訪問もするようになった。
平成6(1994)年に町民会館ができ、毎月図書館での「紙芝居のじかん」や3ヶ月ごとの小ホールでの「おはなしひろば」が始まった。毎週集まって製作や練習を繰り返した。牛乳パックを使っての昔話の人形劇にはメンバーによる生演奏も加わり、昔話の数も増え、親子2世代に渡り楽しみに見に来て下さる方もあり、発足して33年、多くの人に支えられ、続けてきてよかったと思っている。
近隣の小学校やこども園などでの公演も長年続き、人形劇やペープサート等のあとで、たくさんの本を紹介した時の子供達の反応や「また来てください!」のお手紙が活動を後押ししてくれている。
これからも、「本と人との橋渡し」の活動として絵本を子供達に届けることを続けていきたい。
③ 講演『本と人をつなぐ~学校図書館の可能性~』
埼玉県立浦和第一女子高等学校 担当部長兼主任司書 木下 通子 氏
【当日資料はこちら】
(お問い合わせ)
岡山県立図書館 図書館振興課 図書館支援班
TEL 086-224-1269
FAX 086-224-1208
開館カレンダー
- 土曜日・日曜日・祝日
- 休館日
<閲覧室の開館時間>
| 火曜日から金曜日 | 9:00-19:00 |
|---|---|
| 土曜日・日曜日 ・祝日 |
10:00-18:00 |
| 【お問い合わせ先】 |
|---|
| 086-224-1286(代表) |
| 直通電話番号一覧 |
| 問い合わせ内容 |
|---|
| ○調べもの相談(レファレンス) ○資料の予約・リクエスト ○貸出期間の延長 ○利用者カードの登録・更新・紛失 ○デイジー図書、対面朗読サービス カウンター:086-224-1288 |
| ○有料貸出施設の利用 (多目的ホール・情報シアター・ サークル活動室・メディア工房) ○施設見学 086-224-1286 |
| ○図書の寄贈 086-224-1324 |
| ○県立図書館以外でのお受け取り 資料 086-224-1287 |