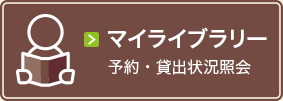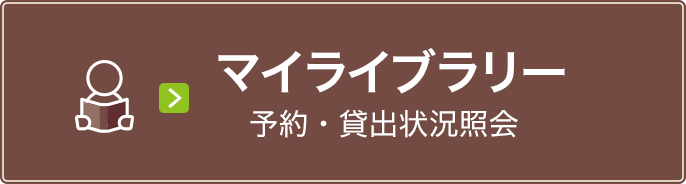とことん活用講座「岡山における近代建築の出現と保存・活用」開催のご報告

開催日時
令和7年1月18日(土)
14:00~16:00
会場
岡山県立図書館
2階 多目的ホール
対象
一般
参加者
78名
講師
上田 恭嗣(うえだ やすつぐ)氏
(ノートルダム清心女子大学名誉教授)
内容
今回の講座では、上田恭嗣氏に、岡山の建築文化とともに、歴史的建造物を保存・活用することの重要性について、お話しいただきました。
岡山県では、明治期に擬洋風建築という日本独自の西洋建築が建てられるようになりました。擬洋風建築は和洋折衷の様式で、県内には法泉寺本堂(和気町)や旧牛窓警察署、旧倉敷幼稚園園舎(:現倉敷市歴史民俗資料館)、旧倉敷町役場(現倉敷館観光案内所)、旧勝田郡役所、旧総社警察署など多くの建物が残っています。特に、かつての岡山県庁の筆頭建築技術者で活躍した江川三郎八(1860-1939)が設計した、旧旭東尋常小学校付属幼稚園舎や旧遷喬尋常小学校は、国指定重要文化財になっています。
本格的な近代建築としては、東京駅の設計者・辰野金吾により、大正7(1918)年に岡山市に二十二銀行が建築されていました。現在は、旧日本銀行岡山支店(現ルネスホール)や、大原美術館の設計者・薬師寺主計による旧中国銀行倉敷本町出張所(現児島虎次郎記念館)、ノートルダム清心女子大学、倉敷紡績所の工場(現倉敷アイビースクエア)、林源十郎商店なども残っています。
戦後に建築された建物では、倉敷市の旧市庁舎(現倉敷市立美術館)や前川國男が設計した岡山県庁舎といった貴重な建物があり、保存改修が行われ現在も活用されています。
上田氏は、このような歴史的建造物を紹介される中で、近代建築を残す意義について、「建物は地域の顔であり、そこにしかない個性あるまちづくりの目印となって、町の歴史や伝統を伝えている。」「次世代に素晴らしい伝統技術や建築の歴史様式・意匠を伝えていかなければならない。」「いい建物は、つぶすのではなく、次への建物用途や維持管理をふまえて、補強やリノベーションして使うべき。」「耐震化が大きな問題。なるべく壊れない建物を考えるのも建築家の仕事の一つである。これからの建物の保存改修には、人の命を守ることを考えることが非常に重要である。」と語られました。
講座では、多数の歴史的建造物の写真を見せながら、建築当時の時代背景とともに、建築技術やデザイン、意匠などをわかりやすく解説されたので、とても説得力があり、参加者の方々はたいへん満足されていたようでした。
また、会場には県立図書館が所蔵する、上田氏の著書、寄稿、研究発表なども展示し、多くの参加者の方にご覧いただきました。
参加者アンケートでも、「建築物の大切さがよく分かりました」「身近な建物の歴史は聞いていてとても楽しかった」等のお声をいただき、大変有意義な講座となりました。

(お問い合わせ)
岡山県立図書館 サービス第二課 自然科学班
TEL 086-224-1317
FAX 086-224-1208
開館カレンダー
- 土曜日・日曜日・祝日
- 休館日
<閲覧室の開館時間>
| 火曜日から金曜日 | 9:00-19:00 |
|---|---|
| 土曜日・日曜日 ・祝日 |
10:00-18:00 |
| 【お問い合わせ先】 |
|---|
| 086-224-1286(代表) |
| 直通電話番号一覧 |
| 問い合わせ内容 |
|---|
| ○調べもの相談(レファレンス) ○資料の予約・リクエスト ○貸出期間の延長 ○利用者カードの登録・更新・紛失 ○デイジー図書、対面朗読サービス カウンター:086-224-1288 |
| ○有料貸出施設の利用 (多目的ホール・情報シアター・ サークル活動室・メディア工房) ○施設見学 086-224-1286 |
| ○図書の寄贈 086-224-1324 |
| ○県立図書館以外でのお受け取り 資料 086-224-1287 |